沖縄の不動産探し、不動産売却&査定事例は
LIXIL(リクシル)不動産ショップ木立へ
(査定事例もご紹介!)
\会員登録不要/ AIマンション査定はこちら
この物件売ったらどのぐらい?

LIXIL不動産ショップ木立の無料査定
見積もり無料!不動産を売りたい方はお気軽にご相談ください。
新着物件
弊社お取り扱い物件をご案内します。


リナージュ那覇市安謝23‐1期(全2棟)2号棟
一戸建て
- 価格
- 5,480万円
- 所在地
- 沖縄県那覇市安謝
- 間取り
- 4LDK


リナージュ那覇市安謝23‐1期(全2棟)1号棟
一戸建て
- 価格
- 5,580万円
- 所在地
- 沖縄県那覇市安謝
- 間取り
- 4LDK


グラファーレうるま市田場5期(全3棟)_3号棟
一戸建て
- 価格
- 3,188万円
- 所在地
- 沖縄県うるま市田場
- 間取り
- 4LDK


グラファーレうるま市田場5期(全3棟)_2号棟
一戸建て
- 価格
- 3,388万円
- 所在地
- 沖縄県うるま市田場
- 間取り
- 4LDK


グラファーレうるま市田場5期(全3棟)_1号棟
一戸建て
- 価格
- 3,088万円
- 所在地
- 沖縄県うるま市田場
- 間取り
- 4LDK


名護市大南4丁目(全4棟)_3号棟
一戸建て
- 価格
- 3,480万円
- 所在地
- 沖縄県名護市大南4丁目
- 間取り
- 3LDK


名護市大南4丁目(全4棟)_2号棟
一戸建て
- 価格
- 3,480万円
- 所在地
- 沖縄県名護市大南4丁目
- 間取り
- 3LDK


名護市大南4丁目(全4棟)_1号棟
一戸建て
- 価格
- 3,480万円
- 所在地
- 沖縄県名護市大南4丁目
- 間取り
- 3LDK

八重瀬町字東風平Ⅱ(全2棟)_2号棟
一戸建て
- 価格
- 4,380万円
- 所在地
- 沖縄県八重瀬町東風平
- 間取り
- 3LDK

与那原町板良敷 3LDK
一戸建て
- 価格
- 3,980万円
- 所在地
- 沖縄県与那原町板良敷
- 間取り
- 3LDK

糸満市照屋5LDK
一戸建て
- 価格
- 3,499万円
- 所在地
- 沖縄県糸満市照屋
- 間取り
- 5LDK

宜野湾市普天間戸建【借地物件】
一戸建て
- 価格
- 1,680万円
- 所在地
- 沖縄県宜野湾市普天間2丁目
- 間取り
- 5LDK
お役立ちコラム
沖縄で新築で平屋を建てたい!メリットデメリット、費用相場や間取り例
2023/11/8
沖縄で庭付き戸建て賃貸に住みたい!選ぶポイントやメリットデメリット
2023/11/6
沖縄で持ち家の戸建てリノベーション|注意点や業者選び、流れを解説
2023/11/1
ローコスト住宅を沖縄で建てるには?自由度の高い5つのコストダウン
2023/09/25
沖縄で40坪一戸建ての価格相場は?一般的な注文住宅建てる建築費用は?
2023/09/20
沖縄で一戸建ての建築費用は?1,000万円~4,000万円それぞれの特徴
2023/09/10
沖縄での土地の探し方とは?予算内で快適な暮らし|流れとポイントを解説
2023/09/5
不動産を買いたい方へ
物件購入の流れ
- STEP1
- お客様のご要望を
ヒアリング
- STEP2
- 物件の資料を
お届け
- STEP3
- スタッフが
沖縄の現地不動産をご案内
- STEP4
- 購入のお申込み
- STEP5
- ご契約成立
- STEP6
- ローンのお申込み・
リフォームのご相談
- STEP7
- ローン決済
購入に関する手続き
- STEP8
- お引渡し・お引越し
木立不動産での
購入が選ばれるわけ
- 選ばれる理由01
- 沖縄那覇市
地域密着型の
不動産会社です。
- 選ばれる理由02
- こだわりの
オリジナルデザイン
戸建て分譲も
行っています。
- 選ばれる理由03
- お客様の視点に立った
ヒアリング・
ご提案
をいたします。
不動産を売りたい方へ
物件売却の流れ
- STEP1
- 売却について
ご相談をヒアリング
- STEP2
- 物件を
調査・査定
- STEP3
- 媒介契約
- STEP4
- 販売活動
- STEP5
- 不動産の
売買契約成立
- STEP6
- 物件のお引き渡し
決算・各種手続き
木立不動産での
売却が選ばれるわけ
- 選ばれる理由01
- インターネット掲載
折込チラシなど
広告・販売活動に
力を入れています
- 選ばれる理由02
- インスペクションと
(建物の劣化などを検査)
瑕疵保険で
物件の価値を
高めます。
- 選ばれる理由03
- 初めての売却でも
大丈夫
わかりやすく
丁寧に対応します。
お知らせ
-
2023/08/4
【オープンハウス開催】糸満市西川《事前ご予約受付中》
-
2020/09/1
台風9号の影響による臨時休業のお知らせ
-
2020/07/23
【オープンハウス開催】西崎3丁目《事前ご予約受付中》




































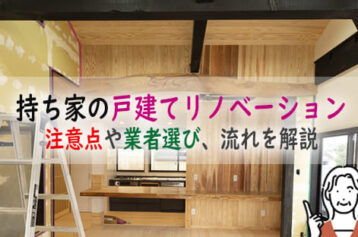
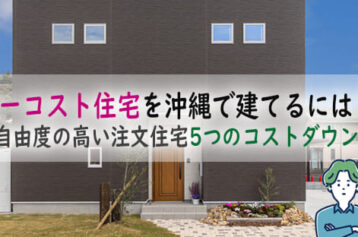


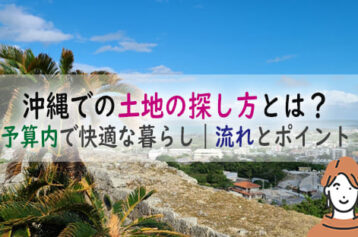


 メールで問い合わせる
メールで問い合わせる




